福井県立大学は、2025年4月に日本初の恐竜学部 恐竜・地質学科を開設しました。福井県立大学恐竜学研究所は新知創造学際ハブの参画機関の一つでしたが、学部開設に伴い、恐竜学部が参画機関となりました。
担当教員の河部 壮一郎 教授に、学際ハブ推進室のメンバーがお話を聞きました。

- インタビューされる人:福井県立大学 恐竜学部 河部 壮一郎(かわべ そういちろう)教授
- インタビューする人:東北大学 金属材料研究所 三河内 彰子(みこうち あきこ)・大石 毅一郎(おおいし きいちろう)
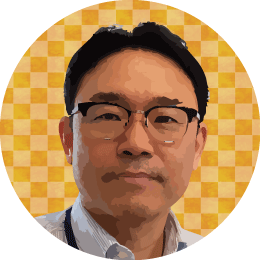
今日は、福井県立大学の河部壮一郎先生にお話を伺います。
よろしくお願いします。
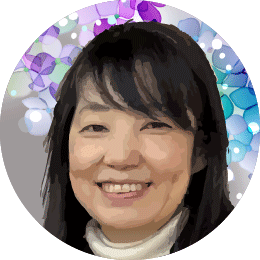
『デジタル時代の恐竜学』が2024年4月10日に出版されました。
これについて教えてください。
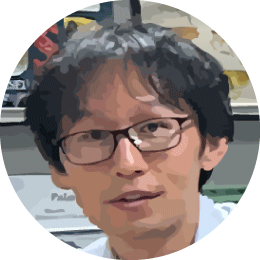
これまでずっと、X線CTを使って化石や現生動物の機能や構造に関する研究をしてきました。
特に恐竜に関してデジタル技術を使った研究をまとめるタイミングだと感じ、出版に至りました。
また、福井県立大学は新たに恐竜学部を立ち上げたこともあり、地元で発掘して地元の化石を研究するなかでデジタル技術を活用し、恐竜研究を次のステップへ進めることが福井県の考える恐竜研究、教育の未来ということを示すこともできるかなと思いました。
恐竜学部の設立について
三河内
具体的にどのような学部ができ、どんなことを進めていこうと考えていますか?
河部
福井県は多くの恐竜化石が見つかる現場があるのが大きな売りです。でも、発掘するためには地質の知識や技術を身につけることが必要です。地質屋さんは山を歩いて地質調査をすることが必要で、そういう人材を輩出したい思いがあります。一方、古典的な古生物学、地質学に加えて最新のデジタル技術も必要です。
なので、両方を融合し育成するカリキュラムを提供することで、未来の研究をリードできるような人材を育てることを目指しています。
三河内
恐竜学部は恐竜の研究中心の研究者だけではないのでしょうか?
河部
はい、その通りです。幅広い地学の知識やノウハウを身に付けるという考え方の学部になると思います。
学際ハブ、そして中性子との出会い
三河内
河部先生は元々恐竜博物館にいらして、大学院生への指導や恐竜学部の設立のために県立大学恐竜学研究所に移られましたが、今回の学際ハブに参画されたきっかけや、今後どのようなことをやっていこうと考えているかを教えてください。
河部
恐竜学部長である西 弘嗣先生の広い人脈のおかげで、今回の学際ハブに参画することになりました。
その中で、中性子を使った研究をされている鬼柳 善明先生(北海道大学名誉教授)とお話しする機会があって、中性子を使って恐竜の骨を観察するというのは世界的にもまだ少ない研究であり、新しい発見が期待できるからやってみようと。そういう話が実践までスムーズに進められる枠組みが整っていたのです。X線CTでものの中身を見るノウハウを持っていましたが、中性子イメージングでさらに新しいことが見えてくるだろうという思いもありました。
三河内
恐竜の研究に中性子の技術を使うことでどういうことができそうですか?
河部
中性子イメージングは私たち(古生物学者)があまり使ってこなかった技術ですが、化石の観察で新しい何かが見えたり、技術などが発展させられたりできるなら面白そうですね。また、こうした学際的な集まりの中で、私たちのノウハウを考古資料の解析に生かすことにも興味があります。
福井県内には興味深い資料がたくさんあることは知っているので、それらに生かしたり開拓・発展させたりできればという思いです。
三河内
学部生や修士の研究などでは、細かいことの積み重ねで見えてくること、なんとなく分かっているけれどもそれをちゃんと証明しようとすると時間がかかるようなこと、そういったものが良いテーマになることがありますね。
河部
はい。ですからまずやってみることが大事というのは研究者はよく分かっていますよね。今回の学際ハブのプロジェクトはそういう空気がありますし、こうやってみたら?と言ってくれる人たちが集まっているように感じるので、すごく心強く思っています。
それに、始まって間もないですが、いろいろな分野の人たちと気楽に話ができるような環境がすでにできていて、思ってもいないような情報やアドバイスを実際にいただいてもいるので、そういう場がもっと増えるととても楽しいと思います。
大石
中性子を使った技術で恐竜を研究することは今までにも考えられたことはあったのでしょうか?
河部
X線CTを使っている方と議論をしている中で、X線よりも透過力が高い中性子を使うと見えるものがあるかもしれない、という話が出たことはあったので、以前から中性子イメージングに興味はありました。
今回のプロジェクトで西先生が鬼柳先生と話されて、「中性子使えるぞ」と聞いたときには、いよいよその技術を使える、一歩踏み出せるという感じでした。
大石
では本当に良いタイミングだったわけですね。こういう機会がないと、自分の知らない分野の技術でどうアクセスしたらいいか分からない場合はハードルが高いと思います。
河部
ハードルは高いですし、「とりあえずやってみよう」というレベルで、知り合いでない人に普通は声をかけられないですよね。今回のプロジェクトはそこが緩くて、「やってみよう」ができそうだなと思います。ですから、分野横断的な掛け合わせがいろいろ考えられそうです。
学際ハブに期待すること
三河内
学際ハブに期待することやリクエストはありますか?
河部
ふわっと始まったものはふわっと終わることがあるじゃないですか。そうならないように、自然解散しないように、その役割を担った方々が中心となってまとめてくださる、つないで束ねてくださる、困ったときには相談できるというのが大事だと思います。
それに、専門分野が少し離れた方から研究を面白いと言ってくださると、自信になりますし継続につながりますね。
三河内
会って話をして顔が見える関係になるとやりやすいですね。
河部
実際に会って話をすると、相手の考えていることの細かいニュアンスが分かります。今回のプロジェクトは、良い意味で緩い集まりとして進められそうというのが、あまりない感じでいいなっていうのがあります。
大石
プロジェクトの開始時はそれが大事だろうと意識的に緩くしているところはあります。時間がたつと自然に厳格になるでしょうが、はじめからそうするとスタートを切りにくいと思って。
河部
当初の不安感は、そんなに緩くてよいのかというものでした。お話ししている中で解消したのですが、あまりそういうグループに接したことがなくて。求められるのが成果や結果というケースが多いので、そのために無理やりスタートさせる必要があるというか。その中で、このプロジェクトではふわっとしていいんだというのが、なんとなく新しい感じがしました。
三河内
時間の使い方が大事ですよね。最後に振り返ったときに何を残せるかですね。
河部
もちろん研究成果を出せるに越したことはないのですが、一方で、5年くらい経って異なる研究分野の人たちで飲みながらいろんな話をする関係ができたというのは、書類には書けないでしょうが実際にはすごく良いことですよね。それができるような気がします。そんな緩さでスタートできるのがすごいと思いましたね。
三河内
本日はありがとうございました。
河部
こちらこそ、ありがとうございました。
関連記事・ページ
- 2025.02.17 YouTube 2025年度新設【恐竜学部】河部先生インタビュー(前編)|福井県立大学(Fukui Prefectural University)

